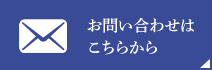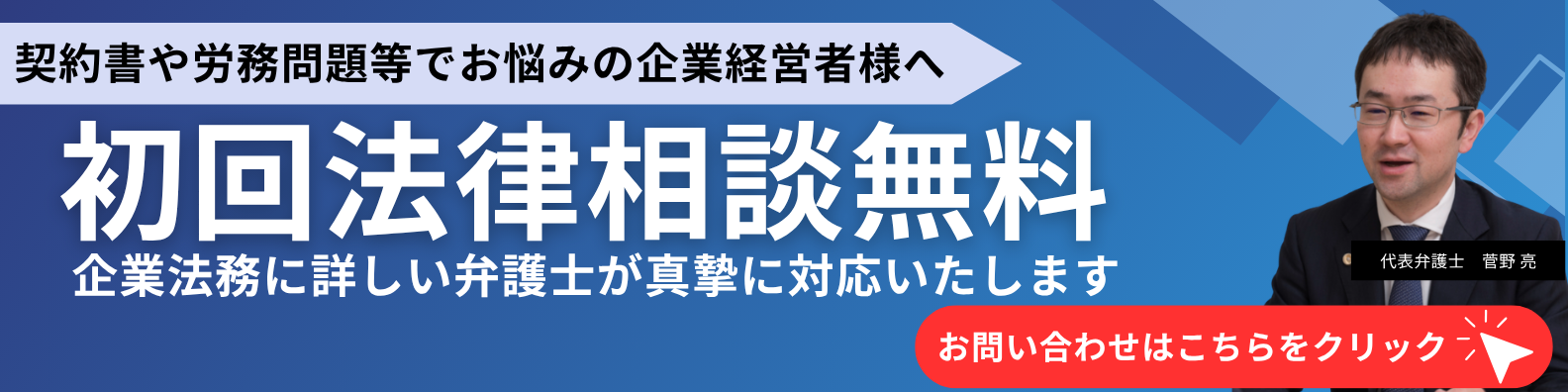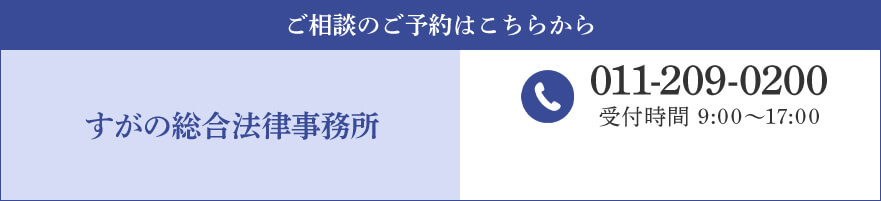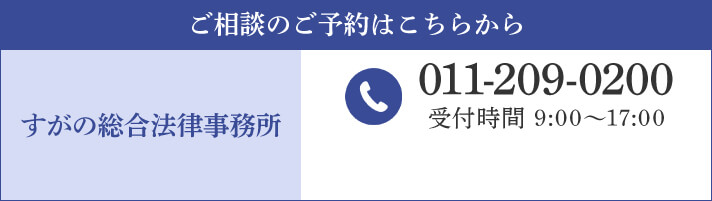近年、取引先との打ち合わせや新規事業の相談において、情報漏えいを防ぐために秘密保持契約書(NDA)を取り交わす機会が増えています。特に経営者の方々から「秘密保持契約書を弁護士に依頼すべきか迷っている」「秘密保持契約書の作成方法が分からない」といった声を多く耳にします。
この記事では、秘密保持契約書(NDA)を作成する目的や基本的な内容、よくあるトラブル事例、注意点、弁護士に依頼するメリットなどをわかりやすく解説します。秘密保持契約書(NDA)の作成やチェックに関する悩みを持つ方にとって、すぐに活用できる情報が詰まっています。
この記事を読むことで、秘密保持契約書(NDA)の基礎から実務的な注意点、弁護士に相談すべきタイミングまで理解できます。特に、重要な情報やノウハウを扱う事業を経営する方、新規取引や業務委託を考えている方に役立つ内容です。ぜひ、最後までご覧ください。
秘密保持契約書(NDA)とは?
秘密保持契約書(NDA)は、業務上知り得た重要な情報を第三者に漏らさないよう義務づける契約書です。NDAは、取引開始前や業務提携の検討段階で締結されることが多く、口頭の約束だけでなく、文書化することで証拠を残す目的があります。
例として、製造業の会社が新製品の開発に関する打ち合わせの前に秘密保持契約書を締結することが考えられます。この際、技術情報や試作データが他社に漏れることを防ぐため、具体的に「秘密情報」の定義を明確に記載し、漏えい時の責任範囲も細かく決めることが重要です。
秘密保持契約書(NDA)は、単なる形式的な契約ではありません。経営上の重要な資産である情報を守るための防衛策であり、損害を未然に防ぐ役割を果たします。特に、営業秘密や個人情報、取引条件など、外部に知られては困る内容を扱う場面では欠かせない契約です。
秘密保持契約(NDA)におけるよくあるトラブル
秘密保持契約書(NDA)を締結しても、完全にトラブルを防げるわけではありません。現場で多いトラブルには以下のようなものがあります。
秘密情報の定義が曖昧で、何が守られる情報か争いになる
契約期間が短すぎて、情報漏えいが発覚した時には期限切れになっている
損害賠償の上限が低く、被害に見合った補償が得られない
例えば、秘密保持契約書に「技術情報」としか記載がないと、どこまでが秘密情報か明確でなかったため、退職した社員が似た技術を別会社で活用してしまうことがあり得ます。このように、曖昧な契約内容は後々の大きな問題に発展します。
秘密保持契約書を弁護士が作成することで、こうしたトラブルを予防するための具体的な条項設計が可能です。
秘密保持に関する契約種別・形式
秘密保持契約書(NDA)には、守るべき情報の性質や取引形態に応じてさまざまな契約種別や形式があります。秘密保持契約書を適切に活用するためには、自社の取引に合った形式を理解し、最適な契約を選択することが重要です。ここでは、秘密保持契約書の主な種別や形式について詳しく解説します。
片務契約と双務契約の違い
秘密保持契約書(NDA)は、大きく「片務契約」と「双務契約」に分けることができます。
片務契約
片務契約とは、一方当事者だけが秘密保持義務を負う契約を指します。例えば、自社が技術情報を提供する場面で、相手方にのみ秘密保持義務を課すケースが典型例です。製品開発を委託する際など、自社が情報を提供する立場で活用されます。
双務契約
双務契約は、双方が互いに秘密保持義務を負う契約です。共同で開発プロジェクトを行う場合や、相互に機密情報を開示する取引では、双務契約が適しています。情報のやり取りが双方向に発生する場合、片務契約では不十分なため、双務契約を選択することが推奨されます。
お互いの情報保護を対等に図る契約とすることが信頼関係構築にも寄与します。
秘密保持契約(NDA)を締結するメリット
秘密保持契約書(NDA)を締結する最大のメリットは、情報漏えいのリスクを事前に減らせることです。契約書があることで、万が一漏えいが発生した場合でも、損害賠償を請求できる法的根拠になります。
また、信頼関係を築く効果もあります。ベンチャー企業が秘密保持契約書の締結によって大手企業との商談がスムーズに進む、というケースなどです。「きちんとリスク管理ができている」と評価されることになるのです。
さらに、社内でも情報管理への意識が高まるため、漏えい防止の社内体制づくりにも繋がります。
秘密保持契約書(NDA)の作成の流れ
秘密保持契約書(NDA)を弁護士に依頼して作成する際には、明確なプロセスを踏むことが重要です。適切な流れを理解しておくことで、スムーズかつ抜け漏れのない契約締結が可能になります。ここでは、秘密保持契約書作成の一般的な流れについて、実際の弁護士業務を基に解説します。
ヒアリングで守るべき情報を整理する
まず、弁護士が依頼者からヒアリングを行います。ヒアリングでは、取引内容、開示する情報の具体的内容、秘密保持の必要性がある理由などを丁寧に整理します。
草案作成でリスクを最小限にする
ヒアリング内容をもとに、秘密保持契約書の草案を作成します。この段階では、秘密情報の定義、秘密保持義務の範囲、契約期間、損害賠償の規定など、実際のリスクに即した内容を盛り込むことが求められます。
チェック・修正で相手方と調整する
草案が完成したら、相手方に提示し、内容の調整を行います。弁護士は相手方の修正提案を精査し、不利な変更がないかを確認した上で適切に再修正を加えます。
交渉が難航する場合もありますが、弁護士が間に入ることで冷静に法的観点から落としどころを提案できるため、スムーズな合意形成が可能になります。
締結で正式に効力を発生させる
最終合意に達したら、署名・押印を行い正式に締結します。電子契約の場合は、所定の手続きをオンラインで完了させます。
実際に多くの企業で見られるのは、契約締結後に「終わった」と油断し、管理が疎かになることです。弁護士が関与している場合は、契約の保管方法や更新管理までサポートすることができるため、安心して運用できます。
秘密保持契約書(NDA)作成の注意点
秘密保持契約書(NDA)は、単にひな形を利用して作成するだけでは不十分です。実際の取引内容や情報の重要度に合わせて、適切な内容にカスタマイズしなければ、思わぬリスクを抱えることになります。ここでは、秘密保持契約書(NDA)の作成時に特に注意すべきポイントを弁護士の視点から解説します。
秘密情報の定義を明確にする
秘密保持契約書(NDA)で最も重要な項目の一つが「秘密情報の定義」です。定義が曖昧であれば、漏えいがあっても「そもそも秘密情報ではなかった」と主張されるリスクがあります。
例えば、製造業の案件では、「製造方法に関する一切の情報」とだけ記載していると、具体的な技術データや試験結果が含まれるかどうかで争いになることがあります。これを防ぐためには、「設計図面」「試験結果」「仕様書」など、情報の種類を明示することが大切です。
契約期間を適切に設定する
秘密保持義務の期間が短すぎると、情報が漏えいした際に責任を追及できなくなる恐れがあります。業界によっては数年後に公開される情報もあれば、半永久的に秘密であるべき情報もあります。
損害賠償条項を検討する
万が一秘密情報が漏えいした場合に備え、損害賠償の範囲や上限額を明確に定めておくことも重要です。特に、被害額が大きくなり得る取引では、上限なしでの賠償を求めるケースもあります。
契約書に損害賠償の上限額が設定されていると、実際の損害額の一部しか回収できないことがあります。このような事態を避けるためにも、弁護士が取引内容に応じた適切な損害賠償条項を設計することが重要です。
秘密保持契約書(NDA)の作成を弁護士に依頼するメリット
秘密保持契約書(NDA)の作成を弁護士に依頼することで、以下のようなメリットが得られます。
実際の取引リスクに即した内容を設計できる
弁護士は、単に条文を整えるだけではなく、実際の事業内容や取引先との関係性を考慮して、個別に最適な秘密保持契約書を設計します。特に、新規事業を伴う場合は、業界特有のリスクも反映させることができます。
トラブルを未然に防げる
弁護士が関与することで、曖昧な表現や抜け漏れを防ぎ、将来の紛争リスクを大幅に低減できます。トラブルが発生した際に、弁護士が作成した契約書であれば証拠力が高く、交渉や裁判で有利に働くことが多くあります。
契約交渉のサポートが受けられる
相手方から修正提案が入った際も、弁護士が法的リスクを判断し、交渉を有利に進めることができます。特に大企業との契約交渉では、弁護士のサポートが心強い味方になります。
秘密保持契約(NDA)に関するお悩みは当事務所にご相談ください
秘密保持契約書(NDA)は、事業の重要な情報を守るための基盤です。しかし、ひな形の流用やネット上のサンプルを参考に作成しただけでは、取引の実態に合わない内容となり、結果的に自社の情報資産を守れないリスクがあります。
当事務所では、秘密保持契約書(NDA)の作成・リーガルチェック・見直し・委任・代行まで、幅広く対応しております。業種や取引先に応じた最適な契約設計はもちろん、交渉支援や契約管理のアドバイスまでワンストップでご提供可能です。
特に、以下のようなお悩みをお持ちの経営者の方はぜひご相談ください。
秘密保持契約書(NDA)をどのタイミングで締結すべきか分からない
既存の秘密保持契約書が自社の取引に適しているか不安
大手企業との交渉で不利にならないようにしたい
経営者の皆様の大切な情報を守るために、実務経験豊富な弁護士が全力でサポートいたします。まずはお気軽にご相談ください。
Last Updated on 2025年6月20日 by kigyou-sugano-law