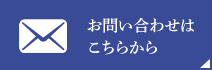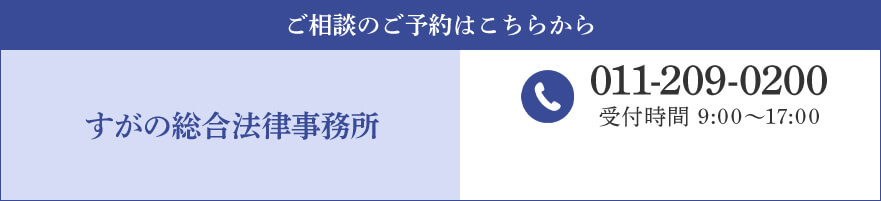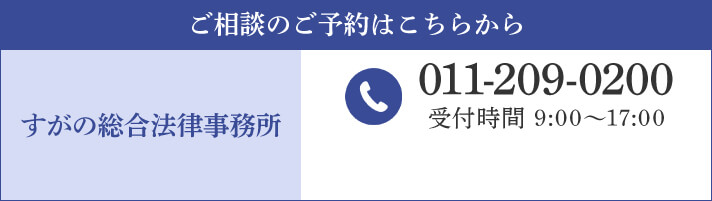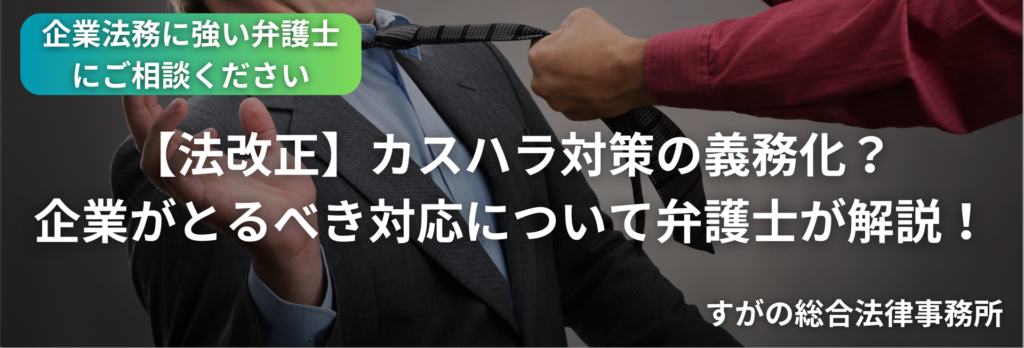
20205年6月4日、労働施策総合推進法が改正されたことにより、カスハラ(カスタマー・ハラスメント)対策が義務化されることになりました。改正された労働施策総合推進法(以下、「改正法」といいます。)は、遅くとも2026年中には施行が予定されています。
現時点ではカスハラ対策が法的に義務づけられているわけではありませんが、企業としては、従業員をカスハラから守るためにも、業績を維持するためにも、適切に対応することが求められている状況です。
法改正の概要について
近年、顧客からの暴言や理不尽なクレーム、不当な要求などにより従業員の心身が重大なダメージを受け、企業の業績にも悪影響を及ぼすケースが急増しています。
「お客様は神様」という社会通念のもとでカスハラ問題が深刻化するにつれ、カスハラもハラスメントの一種として認識されるようになり、企業が従業員を守るための対策を打ち出すべきだという声が高まってきました。
そこで、今回の改正法では、企業がカスハラから従業員を守るために必要な措置を講じるべきことが義務化されたのです。
よくあるカスハラトラブルとは?
カスハラとは、カスタマー・ハラスメントの略称であり、改正法では以下のとおり定義づけられています。
「職場において行われる顧客、取引の相手方、施設の利用者その他の当該事業主の行う事業に関係を有する者の言動であって、その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたもの」
実際によくあるカスハラトラブルとしては、まず、現場の従業員に対して顧客等が大声で怒鳴ったり、暴言を吐いたりして威嚇することが挙げられます。「責任者を出せ!」と迫ったり、人格を否定するような侮辱的な発言をするケースも多々あります。
従業員に対して距離を詰めて圧迫したり、物を叩きつけたり、叩く・小突く・蹴るなどの身体的な暴力が振るわれたりするケースも珍しくはありません。
その他にも、延々とクレームを言い続けることや、土下座など常識の範囲を超えた謝罪の強要、不当な値引きや返品・返金の要求、契約内容にない過剰なサービスの要求などが行われるケースも多いです。
また、昨今ではインターネットが普及していることから、SNSや掲示板サイトなどで店舗や従業員に関する悪評を拡散されるケースが急増しています。
このようなカスハラトラブルを放置すると、疲弊した従業員が心身に不調をきたす可能性が高いですし、離職者が相次ぐ可能性もあります。企業としても、業務効率が低下したり、企業イメージが悪化したりして、業績悪化を招くおそれがあることに注意が必要です。
そのため、企業がカスハラ対策を講じることは喫緊の課題であるといえるでしょう。
法改正で企業がとるべき対応とは
改正法では、カスハラによって労働者の就業環境が害されることのないように、必要な措置を講じることが事業主に義務づけられました。その措置を適切かつ有効に実施するために必要な指針は、今後、厚生労働大臣が定めることとされています。
現時点では正式な指針が示されていませんが、2022年2月に厚生労働省が公表した『カスタマーハラスメント対策企業マニュアル』では、企業がとるべきカスハラ対策として以下のことが掲げられています。
今後示される指針の内容も以下の対策と大きく異なることはないと考えられます。企業としては、早期に以下の対策を進めていった方がよいでしょう。
企業としての基本方針の明確化
まずは、企業のトップとして事業主が、職場におけるカスハラを許さないという基本方針を明確に打ち出すことが必要です。そして、組織として従業員をカスハラから守るという基本姿勢を定め、従業員に周知・啓発し、教育します。
従業員のための相談対応体制の整備
カスハラへの対応を従業員任せにしてはいけません。従業員がカスハラを受けた場合にはすぐ相談できるように、相談窓口を設置したり相談対応者を決めておいたりして、その旨を従業員に広く周知しましょう。
当然ながら、相談の内容や状況に応じて、相談対応者が適切に対応できるようにしておくことも必要です。
カスハラへの対応方法、手順の策定
実際にカスハラに遭遇した際にはどうすればよいのか、具体的な対応方法やその手順は予め定めておくべきです。社内の実情に応じた「カスハラ対策マニュアル」を策定しておくべきでしょう。
従業員への教育・研修
カスハラ顧客へ適切に対応するには、そのためのスキルが要求されます。万全なマニュアルを策定したとしても、それだけで従業員が高度なスキルを習得できるとは限りません。そこで、企業は定期的に研修会を開催するなどして、日頃から従業員を教育することが大切です。
研修では座学だけでなく、過去に職場で発生した事案や経験等を踏まえた事例などに基づくケーススタディを設けると、より従業員のスキルアップに役立つでしょう。
事実関係の正確な確認と事案への対応
顧客等からのクレームの中には、正当な主張もあります。自社に落ち度がある場合には、謝罪や商品の交換、返金などに応じるべきケースもあるでしょう。
正当な主張と不当なカスハラのどちらに該当するかを的確に判断するためには、まず、事実関係を正確に確認することが必要不可欠です。
事実関係を確認するプロセスと、その結果に応じて適切に対応する手順についても、予め定めておきましょう。
従業員への配慮
企業は従業員の安全を確保するとともに、カスハラ被害を受けた従業員の精神面にも配慮する必要があります。
具体的には、従業員がカスハラに遭遇した際には一人で対応させず、複数名で、あるいは組織的に対応する体制を整備しておくことが必要です。
従業員に精神的不調の兆候がある場合には、産業医に相談対応を依頼したり、専門の医療機関への受診を促したりすることも欠かせないでしょう。
再発防止のための取り組み
発生したカスハラ事案がいったん解決しても、同じことが繰り返される可能性は残ります。そのため、同様のトラブルが再発することを防ぐための取り組みも重要です。
定期的に取り組みの内容を見直すことと併せて、トラブル事例を全社員で共有するとともに、ケーススタディを盛り込んだ研修会を定期的に開催することなどが有効となります。
従業員を保護するための取り組み
従業員をカスハラから守るためには、相談しやすい環境を整えなければなりません。
そのために、相談した従業員のプライバシーを保護するために必要な措置を講じた上で、その旨を全従業員に周知することが必要です。
また、相談したことを理由として、その従業員に対して解雇そのた不利益な取り扱いをしてはならない旨を定め、そのことを全従業員に周知することも欠かせません。
カスハラ対策をしない場合罰則はある?
現行の労働施策総合推進法に罰則はありませんし、改正法にも罰則が設けられる予定はありません。したがって、企業がカスハラ対策をしなくても、事業主や担当者が処罰されることはありません。
しかし、改正法の施行後もカスハラ対策をしなければ、厚生労働大臣からの助言や指導、勧告を受ける可能性があり、勧告に従わなければ企業名を公表されることもあります。これにより企業イメージの低下を招き、業績が悪化するおそれがあることに注意が必要です。
また、対策が不十分な状況下で従業員がカスハラ被害に遭った場合は、安全配慮義務違反を理由として、被害を受けた従業員から慰謝料などの損害賠償請求を受ける可能性もあります。これにより、企業が財産的な損失を受けるおそれもあるでしょう。
カスハラ対策を行うメリット
企業がカスハラ対策を行うことには、以下のメリットがあります。ぜひ、積極的に検討を進めていきましょう。
従業員保護
カスハラ対策を行うことは、第一に、働きやすい環境を維持することが可能となり、従業員の保護につながります。また、企業が万全な対策をとることで、従業員から企業や事業主に対する信頼感の強化も期待できます。
その結果、業務効率や生産性が向上し、企業としての業績アップも期待できるでしょう。
ユーザーに対する抑止力
理不尽なクレームや不当な要求を許さないという企業としての基本姿勢を打ち出すとともに、個別の事案に迅速かつ適切に対応していくことで、ユーザーに対する抑止力も期待できます。
カスハラの発生率が低下し、より働きやすい環境を実現することも可能となるでしょう。
採用活動時の訴求
カスハラ被害が社会問題化している昨今において、応募先の企業でカスハラが発生しているのか、企業がカスハラ対策を行っているのかなどの点が、求職者にとっても大きな関心事となっています。
そのため、社内で万全なカスハラ対策を構築していれば、その点が採用活動時の訴求にもなります。その結果、優秀な人材を確保しやすくなり、企業としての継続的な発展も期待できるでしょう。
カスハラ対策を弁護士に依頼するメリット
カスハラ対策を弁護士に依頼すれば、まず、カスハラ対策マニュアルの策定をサポートしてもらえます。マニュアルには、関係法令の内容を踏まえつつ職場の実情に応じた内容を盛り込まなければなりませんが、弁護士のサポートを受けることで、適切かつ実践的なマニュアルの作成が可能となります。
また、弁護士には社内研修会などの講師を依頼することもできるので、従業員の教育もサポートしてもらえます。
さらに、カスハラが発生した場合には、加害者に対する迅速な法的対応を任せることも可能です。万が一、被害を受けた従業員から損害賠償請求を受けた場合にも、弁護士の対応によって穏便な解決が期待できます。
企業のカスハラ対策は当事務所にご相談ください
企業のカスハラ対策は、今後施行される改正法と、それに基づき厚生労働大臣が示す予定の指針に従って構築する必要があります。
現時点では、既に厚生労働省が公表している『カスタマーハラスメント対策企業マニュアル』を主に参照してカスハラ対策を進めることになりますが、このマニュアルは、そのままの形で自社のマニュアルとして流用できる内容にはなっていません。あくまでも、カスハラ対策は自社の実情に応じて構築することが必要です。
当事務所は、札幌で企業法務に力を入れている弁護士事務所です。各種ハラスメント対策を含めて適切な労務管理を実現するために、専門的なアドバイスと実践的な支援を提供しております。
カスハラ対策や、そのほか労務問題でお悩みの企業様はぜひ当事務所にご相談ください。
Last Updated on 2025年9月19日 by kigyou-sugano-law